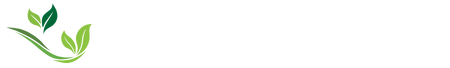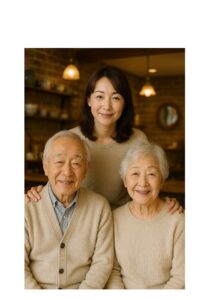36.法定後見制度について
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、後見制度には2種類あります。
前回書きました「任意後見制度」と今回紹介する「法定後見制度」です。
二つとも、判断能力が低下した人をサポートする制度ですが、使い勝手が全く違います。
できる限り「任意後見制度」を活用した方がいいと思いますが、
実際どんな違いがあるかをわかりやすく紹介したかったので、ChatGPTにこんな質問をしました。
「法定後見制度と任意後見制度の違いを分かりやすく表にしてください。」
すると以下の回答をもらいました。
| 項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 利用開始のきっかけ | 判断能力がすでに低下した人(認知症・知的障害など)に対し、家族などが家庭裁判所に申し立てて開始 | 判断能力があるうちに、自分で「将来こうしてほしい」と契約を結んでおき、将来判断能力が低下したら発動 |
| 後見人を決める人 | 家庭裁判所が選任(親族が希望しても、弁護士・司法書士など第三者になることが多い) | 本人が自由に選べる(家族・知人・専門職など) |
| 開始までの流れ | 家族などが裁判所に申立 → 医師の鑑定 → 裁判所が後見人を選ぶ | 公証役場で公正証書を作成(任意後見契約) → 将来、本人の判断力が低下したら家庭裁判所が監督人を選び発動 |
| 後見人の役割 | 本人の財産管理や身上監護を代理・補助する(内容は裁判所が決定) | 契約内容に沿って財産管理や生活支援を行う(内容をあらかじめ自分で決めておける) |
| 柔軟性 | 裁判所の関与が大きく、画一的(本人の希望が反映されにくい場合あり) | 本人が契約内容や後見人を選べるため柔軟で、自分の意思を反映できる |
| 開始できるタイミング | 判断能力が「すでに不十分」になってから | 判断能力が「まだ十分にある」うちに準備できる |
| メリット | すでに判断能力が低下した人でも利用できる/法律に基づき安心感がある | 自分で後見人や内容を決められる/将来の安心を事前に備えられる |
| デメリット | 後見人を自分で選べない/費用が継続的にかかる(専門職が就くと高額) | 契約・発動に手間と費用がかかる/事前に準備しておかないと利用できない |
✅ まとめ
-
法定後見は「すでに困っているときに裁判所が決めて始める制度」。
-
任意後見は「元気なうちに自分で決めて備える制度」。
どちらも「財産や生活を守る」ことが目的ですが、誰が決めるか(裁判所か自分か)といつ準備するか(困ってからか、元気なうちか)が大きな違いです。
【運営者からの一言】
判断能力が低下した後、やむを得ず利用するのが「法定後見制度」です。
高齢者の方で、以下のような考えを持たれている方は、ぜひ任意後見制度をご検討ください。
・認知症のリスクを意識している方
・ご自身が認知症になっても「自分の意思を尊重してほしい」と強く思う方
・安心して老後を過ごしたい方
・家族や周囲に迷惑をかけたくない方
家族信託と併せてうまく活用したいですね。
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!