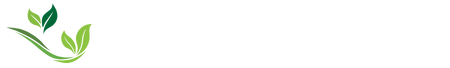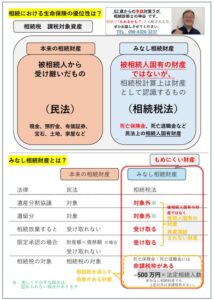19.家族信託(民事信託)について①(メリットとデメリットは?)
私が仕事をするうえで、「家族信託(民事信託)」という言葉を聞く機会が最近増えてきました。
とはいえ、一般の方がどの程度「家族信託(民事信託)」のことをご存じかをChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
・「よく理解している」と答えた人は約21%
・「聞いたことはあるが詳しく知らない」は約52%
・「今まで聞いたことがない」は約26%
この結果を見て、家族信託のことをこのコラムでお伝えしたいと思いました。
いつものように、客観的な情報をお伝えしたかったので、ChatGPTにこんな質問をしました。
「家族信託(民事信託)はどんな人にメリットがあるのですか?」
家族信託(民事信託)は、財産管理や相続対策の手段として注目されていますが、特に以下のような方々にメリットがあります。
✅ 1. 認知症対策をしたい人
将来、認知症などで判断能力を失った場合、通常は財産を凍結され、売却や運用ができなくなります。
家族信託では、あらかじめ信頼できる家族に財産管理を託すことで、凍結を回避できます。
✅ 2. 親が高齢で、今後の財産管理に不安がある家族
たとえば、高齢の親が不動産を所有していて、その管理や売却が必要になる可能性がある場合。
家族信託により、子が代わりに管理・処分できるようになります。
✅ 3. 二次相続まで見据えた相続対策をしたい人
遺言では一次相続(例:夫→妻)の指定しかできませんが、
家族信託なら「夫→妻→子」といった二次相続以降も含めた指定が可能です。
✅ 4. 障がいのある子や、浪費癖のある子がいる人
遺産を一括で渡すと心配なケースにおいて、
信託で財産を小分けに給付するなど、柔軟に管理・給付のルールを決められます。
✅ 5. 共有名義不動産の問題を避けたい人
複数人で共有している不動産は、管理や売却に全員の同意が必要でトラブルのもとに。
家族信託により、スムーズな運用・処分ができるようになります。
✅ 6. 後見制度に頼りたくない人
成年後見制度は自由度が低く、費用や手間がかかることも。
家族信託なら、自分の希望に沿った管理を、信頼する家族に任せられます。
✅ 7. 会社経営者の事業承継対策をしたい人
株式などの引継ぎにおいても、家族信託を活用すれば議決権や配当の受取などを柔軟に設計できます。
実は、高齢のアパートオーナー様から、家族信託のことをよく相談されます。
「家族信託をやった方がいい?」と聞かれたとき、
私は「ぜひ検討を!」と伝えます。
この点もChatGPTに聞いてみました。
「高齢のアパートオーナ-が家族信託をするメリットとデメリットは?」
✅ 高齢のアパートオーナーが家族信託をする【メリット】
1. 認知症になってもアパート経営を継続できる
-
オーナーが認知症になると、契約や修繕、売却などができなくなる(=財産凍結)。
-
→ 家族信託をしておけば、子などの受託者が代理してアパート経営を継続可能。
2. 修繕・建替え・売却などもスムーズに行える
-
築古アパートでは、タイミング良く修繕・建替え・売却する判断が重要。
-
→ 信託契約にそうした権限を入れておけば、タイムロスなく対応可能。
3. 賃料収入は引き続き本人(親)の生活費にできる
-
アパートからの家賃は、受益者であるオーナー本人に還元できるよう設計できる。
4. 二次相続まで見据えた「資産承継の流れ」が作れる
-
「親 → 長男(管理)→ 長男が死亡したら孫へ」など、承継の順序をあらかじめ設定できる。
-
遺言ではここまでできない。
5. 成年後見制度を回避できる
-
後見制度に頼ると、費用が高い・自由に売買できない・手続きが面倒などの課題がある。
-
→ 家族信託なら、親族が柔軟かつ自主的に財産管理できる。
⚠️ デメリット・注意点
1. 税務処理・登記などが複雑
-
アパートの登記名義変更、家賃の受け取り口座変更、契約書の名義変更など、実務が煩雑。
-
税理士・司法書士・不動産管理会社と連携が必要。
2. 相続税評価額・課税方法は変わらない
-
家族信託しても、相続税そのものは原則として軽減されない(信託は税回避策ではない)。
3. 受託者選びに慎重を要する
-
不適切な人に受託者を任せると、財産が不適切に扱われるリスクあり。
-
信託監督人や専門家の助言を入れるのが安心。
4. 遺留分や他の相続人とのトラブルリスク
- 実質的に「資産の偏った管理・承継」に見えると、他の相続人から不満が出る可能性がある。
【運営者からの一言】
オーナー様の認知症や判断力が低下した時に、代わりに財産の管理・活用・処分を任せる契約が「家族信託」なので、2.3.4.のリスクは見据えなければならないです。その際に頼りになるのが1.の専門家です。
当相談所の家族信託の専門家は、累計500件以上の家族信託相談実績があり、多くの金融機関とも提携されているファミリアグループの國枝司法書士(顔写真とホームページをご紹介)です。愛知県内随一の実績の持ち主です。お人柄が抜群で、私がトンチンカンなことを聞いても優しく、丁寧に教えてくださいます。ぜひ、ご紹介させてください。
🔍 具体的な活用例
築30年のアパートを持つ80歳の父が、長男に信託するケース
-
父(委託者・受益者):引き続き家賃を受け取り、生活に活用
-
長男(受託者):管理会社と契約し、必要に応じて修繕や建替えも可能に
-
契約には「父が亡くなったら、次は長男が受益者になる」と規定
→ 管理と承継のスムーズな流れができ、他の兄弟にも不公平感が出ないよう遺留分対策も検討
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 認知症対策・スムーズな賃貸運営・柔軟な承継・後見制度回避など |
| デメリット | 実務の手間・税務効果は限定的・家族内トラブルの火種になることも |
| 向いている人 | 高齢のアパートオーナー、認知症リスクがある人、資産を特定の子に託したい人 |
認知症については、コラムの
「9.認知症。発症する年齢と亡くなるまでの期間は?」をご覧ください。
ここでは、2024年時点のデータをお示ししています。
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!