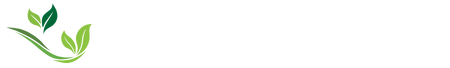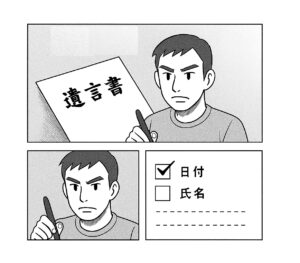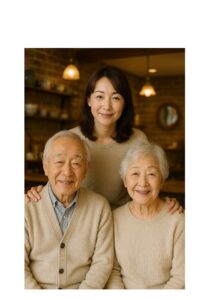34.任意後見契約について①(メリットとデメリットは?)
「任意後見契約」って聞いたことがありますか?
任意後見契約とは、将来、自分の判断能力が低下したとき(認知症など)に備えて、
信頼できる人に「財産管理」や「生活のサポート」をしてもらうよう、元気なうちに契約しておく制度です。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
🔧 仕組み
-
契約するのは「本人」と「後見人になってくれる人」
-
内容は、「どんな支援をしてほしいか」「財産をどう管理してほしいか」など
-
公正証書で契約を作ります(口頭や私文書では不可)
🕒 いつから始まる?
任意後見契約は、契約しただけではスタートしません。
-
本人が元気な間 → 契約だけしておく(準備段階)
-
認知症などで判断能力が低下 → 家庭裁判所に申し立て
-
裁判所が「任意後見監督人」を選任 → この時点で契約が発効・後見開始
✅ どんな人が利用している?
-
将来、認知症になる前に備えておきたい人
-
ひとり暮らしで頼れる親族がいない人
-
自分の希望通りに財産の管理や介護方針を決めておきたい人
【運営者からの一言】
任意後見契約も、自身の判断能力があるうち(認知症などになる前)に契約をしなければいけません。
家族信託(民事信託)と同様、早めに契約することを強くお勧めします。
意思能力が失われたら、法定後見制度を使わなければならなくなります。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
✅ メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自分で後見人を選べる | 信頼できる人(家族・専門家など)を事前に指定でき、望まない人が後見人になるリスクを避けられる |
| 開始時期を自分で決められる | 判断能力が低下した「その時点」で発効するため、必要になるまで介入されない |
| 支援内容を細かく決められる | 財産管理・介護・医療など、どこまで支援してほしいかを契約で細かく指定できる |
| 公正証書で確実性が高い | 契約は公正証書で作成するため、法的な効力が強く、トラブル防止につながる |
| 成年後見では対応できない「自分の希望」も盛り込める | 施設の選び方、終末期医療の方針、財産使途の希望なども契約書に記載可能 |
⚠️ デメリット・注意点
🔎 まとめ
任意後見契約は、「将来の認知症リスクに備え、誰に、どのように支えられたいか」を自分で決めておける仕組みです。
-
「家族に迷惑をかけたくない」
-
「勝手に財産を使われたくない」
-
「自分の希望通りに施設や医療を選んでほしい」
と考える方には非常に有効です。
一方で、元気なうちの準備・費用負担・契約内容の具体性がポイントになるため、契約時には専門家(司法書士・弁護士)に相談しながら進めることが大切です。
【運営者からの一言】
補足説明です。
身内が任意後見人になった場合は 「報酬なし」にできます。(実務ではそうすることが多いようです。)
ただ、そのような場合でも、任意後見監督人が選任が必要です。
任意後見監督人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるのが一般的で、上述のように費用は月額1万~3万円が相場のようです。
繰り返しになりますが、
自分の判断能力が低下したときに備えるために、任意後見契約と家族信託(民事信託)はどちらも大切な制度です。
それぞれどんな場合に使うかについて、簡単に触れておきます。
・任意後見制度→「生活や身の回りの支援(生活や介護サポート)」が目的。
・家 族 信 託→「財産の管理・承継(財産の運用・承継対策)」が目的。
と思っていただければいいです。
両方を組み合わせることで、認知症になった時も一定程度の安心を得ることができると思います。
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!