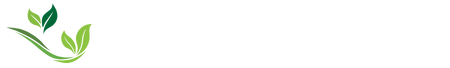33.遺留分(一定の相続人に法律で保障された「最低限の相続分」)
前回の「32.「遺言執行者」を指定することについて③(作り方、作成上の留意点は?)」の最後にも書きましたが、今回は「遺留分」について書きます。
この制度は、財産を相続するうえでとても大事ですので、ぜひ確認してくださいね。
まずは前提です。
遺言書がない場合は、遺産は相続人(遺産を受け継ぐ人)全員で話し合って分けます。
このときの基準になるのが「法定相続分(法律で決められた取り分)」です。
じつは、この法定相続分は「遺留分(最低限もらえる分)」でもらえる取り分より多いので、あえて遺留分を主張する必要はありません。
一方、『思い通りに』、そして“もめずに”『引き継ぎたい』人は、遺言書を書きます。
遺言書を書けば、法律どおりの割合ではなく、自分の希望に沿った分け方ができるのです。
簡単に言うと
・遺言書がない → 法律の割合どおりに分ける(もめやすい)。
・遺言書がある → 自分の希望どおりに分けられる(ただし最低限の権利=遺留分は守られる)。
この最低限の権利が「遺留分」です。
もうちょっと詳しくお伝えしたいので、「遺留分って何ですか?」とChatGPTに聞いてみました。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
遺留分(いりゅうぶん)とは、
「法定相続人に法律上保証された、最低限もらえる相続分」のことです。
🔍 なぜ遺留分があるの?
たとえば遺言で
「全財産を愛人に相続させる」
と書かれていた場合でも、
配偶者や子どもがまったくもらえなくなるのは不公平ですよね。
そこで法律は、一定の相続人に対して
「最低これだけは取り戻せますよ」という取り分を保証しています。
→ それが 遺留分 です。
✅ 遺留分を請求できる人(=遺留分権利者)
-
配偶者
-
子ども(または孫)
-
両親(子がいない場合のみ)
※兄弟姉妹には 遺留分なし
📏 遺留分の割合(ざっくり)
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | 法定相続分の半分 |
| 子ども | 法定相続分の半分 |
| ご両親 | 故人に配偶者がいる場合 ➡法定相続分の半分 相続人がご両親のみの場合 ➡法定相続分の1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし |
💡 まとめイメージ
遺言で「〇〇に全部あげる!」と言っていても、
配偶者や子は “一定割合までは取り戻せる権利” を持っている。
→ それが 遺留分。
【運営者からの一言】
遺言書を書く場合は、できる限り遺留分を意識すべきです。
遺留分を無視して書くと、
・遺留分を侵害された相続人(配偶者や子)が請求すれば、結局遺留分相当額を支払わなければならない。
・「自分だけ少ない・ゼロだ」と感じた相続人が、不満や争いを起こす可能性が高まる。
など、トラブルなどの原因になりますので、ご注意ください。
ここで盲点になりやすい事例を紹介します。
以下の場合は、じつは”遺留分を気にせずに”遺言書を書いてほしいと私は思います。
・子、親がいなくて相続人が「妻と”自分の兄弟姉妹”」の場合 かつ
・財産のすべてを妻に渡したい場合
理由は、遺言書がないと、妻だけでなく兄弟姉妹にも相続する権利が発生してしまうからです。
多くの人は「全部妻が相続できる」と思い込んでいますが、実際には兄弟姉妹が取り分を主張でき、トラブルにつながることがあります。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書で「すべて妻に相続させる」と書いておけば、安心して妻に全財産を残すことができるのです。
気になる方は、専門家の方に相談してみてくださいね。
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!