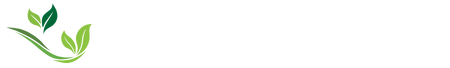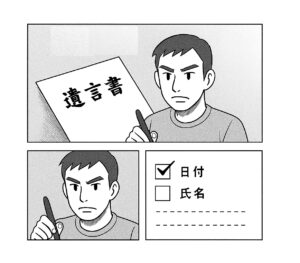32.「遺言執行者」を指定することについて③(作り方、作成上の留意点は?)
前回に引き続き、「遺言執行者」についてです。
「30.「遺言執行者」を指定することについて①(メリットとデメリットは?)」
でも書いたように、
公正証書遺言とセットで話をされる場合が多いのですが、
じつは自筆証書遺言でも指定することができます。
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
遺言執行者の指定方法と指定時の留意点を、実務的な流れに沿って整理します。
1. 遺言執行者を指定する方法
(1) 遺言書で指定する
-
自筆証書遺言・公正証書遺言いずれでも可能。
-
遺言文中に、明確に「遺言執行者を〇〇とする」と書く。
-
例:
第○条 遺言執行者として、住所〇〇氏名〇〇を指定する。
(2) 遺言で「指定権者」を決める
-
遺言書で「遺言執行者は〇〇が選任する」と定め、その人に選ばせる方法。
-
本人が亡くなった後に、指定権者が人選して家庭裁判所に申し立てる。
(3) 家庭裁判所で選任してもらう
-
遺言に指定がない場合や、指定された執行者が辞退・死亡した場合に、相続人等の申立で家庭裁判所が選任。
2. 指定する場合の留意点
① 選任者の信頼性・適格性
-
誠実で事務処理能力があることが最重要。
-
親族の場合は他の相続人との利害関係に注意。
-
専門家の場合は、過去の相続案件の実績や費用体系を事前確認。
② 代替者の指定
-
指定した人が就任できない場合に備えて予備の遺言執行者も書いておくと安心。
③ 複数指定の可否
-
複数人を共同執行者にすることも可能だが、意思決定が遅くなる場合がある。
-
役割分担(例:不動産は司法書士、預貯金は税理士)も可能。
④ 報酬の定め
-
無償・有償どちらも可能。
-
有償にする場合は、計算基準や支払い方法を遺言に明記しておくと相続人間での争いを防げる。
⑤ 財産の種類と所在地を考慮
-
不動産や海外資産、非上場株式など複雑な財産が多い場合は、その分野に強い執行者を選ぶ。
⑥ 遺言の形式
3. 指定文のシンプルな例
第○条 遺言執行者として、下記の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇(生年月日:昭和〇年〇月〇日)
報酬は、遺産総額の〇%を限度として支払うものとする。
この方法を押さえておけば、遺言執行者をめぐる就任拒否や争いをかなり減らせます。
ご自身の想い示して、その通りに実現することは、残されたご家族がもめないようにすることに繋がります。
「もらえるものはできるだけ多くもらいたい」
「兄貴はあんなに援助してもらったから、法定相続分なんか関係ない。この財産は俺がもらう!」
など、親御さんのお葬式が終わった後くらいから、いろんな意見が出てくるものです。