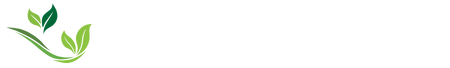31.「遺言執行者」を指定することについて②(メリットとデメリットは?)
前回に引き続き、「遺言執行者のメリットとデメリット」についてです。
前回同様、相続対策の中で確実性の高さを確認する場合は、ここをクリックしてみてください。
ChatGPT:
ChatGPTの答えは、以下の通りでした。
遺言執行者の選び方比較表
| 選任対象 | 費用目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 親族(配偶者・子など) | 無償〜数万円(実費のみ) | - 財産や家族事情を熟知 - 信頼関係が前提で動ける - 費用を抑えられる |
- 他の相続人から不公平感が出やすい - 専門知識が不足し、手続きが滞る可能性 - 感情的対立に巻き込まれやすい |
| 弁護士 | 50〜200万円程度(遺産規模や内容による) | - 中立的立場で法的に確実な執行 - 相続争いへの対応が強い - 複雑・紛争性の高い案件に向く |
- 費用が高額になりやすい - 財産管理の実務面では別の専門家が必要な場合あり |
| 司法書士 | 20〜80万円程度 | - 不動産登記や名義変更に強い - 費用が比較的抑えめ |
- 法律紛争対応はできない(調停・訴訟代理不可) |
| 行政書士 | 10〜50万円程度 | - 預貯金解約や事務手続きに強い - 費用が比較的安い |
- 法的紛争対応や登記はできない |
| 税理士 | 30〜100万円程度(相続税申告料込みの場合あり) | - 財産評価・税務申告まで一括対応可能 - 事業承継案件にも強い |
- 登記や法律紛争対応は別途依頼が必要 |
| 信託銀行(遺言信託) | 数十万〜数百万円(報酬規定あり) | - 全国にある財産の一括管理が可能 - 大規模遺産・全国分散資産に強い |
- 高額な報酬 - 事務処理がマニュアル的で柔軟性に欠ける場合あり |
実務での選び分け目安
-
仲が良く財産が単純 → 親族
-
不動産が多い → 司法書士
-
税務も一緒に解決したい → 税理士
-
争いが予想される → 弁護士
-
高額・全国分散の資産 → 信託銀行
【運営者からの一言】
ChatGPTは、わかりやすい表を作ってくれました。
費用面も考慮すると信頼できる親族に頼みたいのですが、揉めそうなら専門家だと思います。
いずれにしても、揉めないようにするには、
事前にご自身の想いをご家族と共有することで、揉める可能性をできる限り低くするべきだと思います。
改めて、どんな対策をするかは、「相続対策ができる方法」を参考にしてみてください。
費用面も考慮すると信頼できる親族に頼みたいのですが、揉めそうなら専門家だと思います。
いずれにしても、揉めないようにするには、
事前にご自身の想いをご家族と共有することで、揉める可能性をできる限り低くするべきだと思います。
改めて、どんな対策をするかは、「相続対策ができる方法」を参考にしてみてください。
愛知県全域【名古屋市、西尾張地方(一宮市、稲沢市、江南市、あま市、北名古屋市など)、東尾張地方(春日井市、小牧市、瀬戸市、日進市、尾張旭市など)、西三河地方(豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、刈谷市など)、東三河地方(豊橋市、豊川市、蒲郡市など)】の方の相続相談にご対応いたします。相続対策は無料相談から!